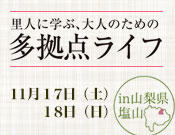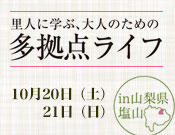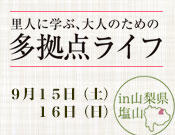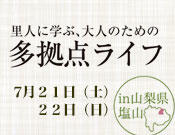COLUMNそばの歴史・起源・定義って何?
「年越しそば」に象徴されるように、そばは、日本人に非常に長く、そして深く愛されているものです。
ただ、この「そば」という魅力的な食べ物の歴史を正確に解説できる人はそう多くはないのではないでしょうか。
今回は、この「そば」の歴史や起源、そしてその定義について見ていきましょう。

■そばの歴史は縄文時代から!
驚く人も多いかもしれませんが、そばの歴史は縄文時代にまでさかのぼると言われています。そばの花粉の存在が、高知県の地層から発見されており、これが日本における最古の「そば」だとされているのです。もっとも、このそばは、日本を原産地としているわけではありません。その起源は大陸、特に中国にあったと言われています。現在は、「朝鮮半島から現在の長崎の辺りに伝わり、そこから広まっていったのではないか」と推測されています。
もっとも、この頃のそばについては、「文字」として残されているわけではありません。あくまで花粉の状態から推測されているにすぎないのです。
そばが文献に登場するようになったのは、平安時代になってからです。平安京に遷都されたのが794年ですが、その3年後に、「属日本書紀」というものが出来上がります。しのなかで、「米があまり育たないから、代わりにそばなどを育てるように」という記述があったと言われています。
ただ、この文章を読んで、不思議に思う人もいるかもしれません。ここではそばが、「お米の代わり」というポジションで話されているのです。このことからも推測できるように、この当時のそばは、今で言う「麺類」のかたちではありませんでした。そばの実を食用としており、これをそのまま茹でるなどして主食として用いていたわけです。
このような時代はその後も非常に長く続きます。1600年代、日本の食文化が大きく花開く(この時代にはすでにグルメガイドが登場していました)江戸時代に至るまでの約800年もの間、そばは「麺」というかたちになることがなかったのです。
私たちは今、「そば」と聞くと、当たり前のように「麺」のかたちをとっているものをイメージします。しかし実のところ、そばの歴史のなかでは、麺類であった時代の方が短かったわけです。今でも広く使われている手法である「つなぎを使って作るそば(麺)」が朝鮮の僧侶によってもたらされたのを契機とし、そばは現在のような「麺」という形態をとるようになりました。
これは非常に画期的な変化だったと言えるでしょう。一度「麺」というかたちになると、それは広く受け入れられるようになりました。江戸時代は中食(屋台などで物を買って帰り、家で食べる形式。今で言うテイクアウトや惣菜)も発展していましたし、外食という形式も広く利用されていました。一部のお金持ちを除き、多くの人が額に汗をして、必死に働いていた時代。短い時間で茹であげることができ、すぐに食べることのできる「麺類としてのそば」は、労働階級を含め、多くの人に愛されるようになりました。
1700年代からは屋台もたくさん立つようになります。コンビニエンスストアがなかった時代にあって、夜の21時ごろから店を開け始める「夜鷹そば」は、小説やドラマなどの舞台にもよく登場します。ちなみに現在では、「コシがあって、ハリがあるそば」が「うまいそば」とされていますが、かつては柔らかい口当たりのそばも多くの人が好んで食べていたそうです。特に1800年の初頭はこのようなかたちのそばがはやったのだとか。
このように見ていくと、私たちが当たり前に見ている「そば」というものは、実はさまざまな変化を経ているのだということが分かりますね。
■そばの定義
さて、ここまでそばの歴史について見てきましたが、それではそばの定義というのはどのようなものなのでしょうか。実は、衝撃的なことに、「そばの概念」というものはたった1つの条件でしか定義づけされていません。それが、「そのそばのなかに含まれている成分のうち、30パーセント以上がそば粉であること」です。
言い方を変えれば、これさえ守っていれば、たとえ残りの70パーセントが小麦粉などであっても「そばである」と断言することができてしまうと言われています。これと差別化するために、「十割そば」などの売り文句が使われています。これはそば粉だけを使って作り上げるそばです。そのため、そばの香りがもっとも強く味わえます。「十割がそば粉だ」という点は一緒であっても、打ち上げる人の技術やどんなそば粉を使うか、どのように調理するかで味も変わってくるので、それを食べ比べる楽しみもあります。
これに比べて、「つなぎを使ったそば」は、ともすれば邪道扱いをされてしまうことがあります。しかし「つなぎに何を使うか」によってまったく味は変わってきます。たとえば、新潟県の名物である「へぎそば(海藻の一種である布海苔(ふのり)を使って作るそば)」を、「邪道だ」と断言できる人は決していないでしょう。
■まとめ
そばの歴史は平安時代から始まっており、非常に長い歴史のある食べ物です。最初は米の代わりとして食用されており、麺の形をしていなかったそばですが、今ではすっかり家庭に定着した食べ物となりました。スーパーなどで○割そばなどと、様々な商品が販売されているように、そばの定義は「そば粉が30%含まれている」のみです。そばを買うときにも、そば粉が何割入っているのかを見てみると、面白い発見があるかも知れませんね。
蕎麦料理マイスター講座のご紹介
家庭で蕎麦打ち、おもてなし
最近テレビやネットでは、蕎麦でダイエットが出来る!といったフレーズをよく見かけるようになりました。
実際蕎麦は、女性にとって嬉しい栄養や美容効果が高いことで知られており、最近では蕎麦打ちをご自宅で行う方もいるそうです。そんな蕎麦ブームが来ている中、この講座では打ち方だけではなく、蕎麦を美味しくいただくためノウハウを蕎麦名人がしっかり教えます!家族やママ友に振る舞える魅力的な日本の女性を目指してはいかがでしょうか?