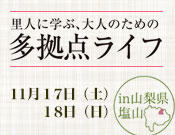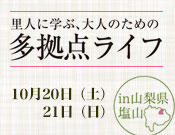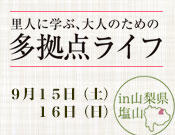FEATURE「嫁と僕のおけいこライフ」*後編 〜人生に必要なもの。それは勇気と想像力、そしてコーヒーブレイク〜


<登場人物>
僕=マサル。静岡県出身の39歳。実家はお茶農家。広告編集プロダクションに勤務。幸せを感じるのは、嫁不在の休日(理由:好きなだけゲームができるから)。今一番欲しいのは可愛い柴犬。
嫁=よしえ。大阪府出身の45歳。物書き。町歩きエッセイや児童小説を執筆。平日の午後は、テレビのワイドショーと“会話しながら”コーヒーブレイクするのが至福の時間。
<前編のあらすじ>
平和を愛する真面目サラリーマンの「僕」と、ぐうたらライフを愛する「嫁」が参加したのは、「カフェスタイル実践講座」。ペーパーフィルターとプレス式の道具を使った2種類のドリップ方法を体験。味の違いに感動する僕だったが、ふいに悪夢のコーヒーブレイクの思い出がフラッシュバックする……。

コーヒー&ラテアートスペシャリスト講座とは?
世界のカフェスタイル体験レッスンの申込みはこちらから
嫁の一家はコーヒー党だ。朝はコーヒーを飲まないと始まらないという。一方、うちの実家にはコーヒーメーカーはおろか、インスタントコーヒーさえない。なぜならお茶農家だから。
その代わり、エスプレッソ並に濃い緑茶を煎れる技もあるし、出汁のように味わい深いお茶で、ここぞという時に人を和ませることもできる。それが僕の矜持であり、唯一無二の特技だった。
その特技を生かすチャンスは意外なタイミングでやってきた。
今から10年ほど前の出来事だ。
僕がまだ独身生活をエンジョイしていたある夏休み、交際中だった嫁と旅行をしようということになった。当時、嫁の父は北陸福井に赴任中で、それなら顔を出しがてら、東尋坊でも行こうかという場当たり的なノリだった。嫁の実家には、それ以前にも仲間たちと訪れたことがあったし、僕には彼女の両親に挨拶に行くというかしこまった心構えなどまったくない脳天気なぶらり旅だった。

コーヒー&ラテアートスペシャリスト講座とは?
世界のカフェスタイル体験レッスンの申込みはこちらから
「よく来てくれたねえ。遠かったやろう、ゆっくりしてね」
「魚は旨いし、肉もええの買ってあるし、ビールもチューハイもいっぱいあるで」
玄関で出迎えた嫁の両親の過剰なはしゃぎっぷりに、この時点で僕は緊張感を持つべきだった。
僕らは当初の計画通り、観光スポットに出かける準備を始めた。
「倉本聰のドラマの時間には帰って来るから」
僕らが出かけることに不服そうな両親に嫁はそう言い残し出掛けた。
しかし慣れない土地での散策は時間が読めず、あっという間に日は暮れた。
「もう少し寄り道しよ。遅くなるって電話するから」と嫁が言った瞬間、二人とも携帯の充電が切れた。
そして時刻は、すっかり倉本聰ドラマも後半にさしかかった頃。
駅前でタクシーを待っていると向こうから「こらあ〜! こんなに遅くまで何してるねん!」とただならぬ絶叫が聞こえた。
嫁の父(以後オトン)ヒロシの登場である。
「心配で車で探しに来たんや、怖い人らに絡まれたらどないすんねん」
その時の僕にとって、もっとも怖い人は、目の前のオトンだった。

帰宅すると、茶の間には豪勢な料理がすっかり色を失い並んでいた。
全員分のビールグラスはコースターの上に透き通ったまま置かれている。
それを見た瞬間、嫁が突然キレた。
「頼んでないもん、こんなん頼んでへんのに。うちらはただ観光したかっただけやのにいいい!」「あほなこといいな!」
しゃくり上げる嫁とオカンの狂想曲。
火種の張本人である父ヒロシは、そんな母娘の様子に完全にひるみ、「のどが乾いたからジュース買いに行くわ」と戦線離脱。
窒息しそうな惨劇現場にたたずむ、完全部外者の僕。
こんな時どうすれば……。そうだ。お茶だ!
僕は「お茶をいれましょう」とオカンに優しく囁いた。
「そやな、静岡のお茶持ってきてくれたんやったな」
ヤカンからお湯がしゅんしゅんと沸き立つ。実家の新茶を急須に入れ、お湯が適温まで冷めるのを待つ。こんな時ほど時間をかけて煎れるのだ。
オカンがテレビをつけると、いきなり軍服姿のビートたけしが現れた。
「お父さん、これ一緒に観たかったんか?」とオカン。
沈黙が続く。
「あんまオモシロないな」と嫁がぽつりと言う。
「そやな」とオカン。
「お茶入りました!」
僕の中では最高に心を尽くした新茶の一杯。
「ごめんな、マサルくん。こんなことになってしまって」
気を取り直したオカンが言う。間もなくカラカラとと引き戸が開く音がして、しょぼくれたオトンが帰ってきた。とりあえず内容がさっぱりわからない戦争ドラマに集中するフリをしながら、ズズーと鳴る四つの湯のみ。
「おいしいな」
「おいしいわ」
「うん…旨いわ」
なんとか茶の間は、平常を取り戻した。
お茶はいさかいを止め、平和をもたらす最高のアイテムだ。僕はそう確信した。

翌朝、コーヒーメーカーで豆が砕かれるブビーンという音で目が覚めた。
「マサルくん、ちょっといい?」
朝の光が差し込む和室の枕元に、オカンが正座していた。
「おふぁようございます……」僕は目をこすりながら起き上がった。
「昨日、お父さん、マサルくんからええ話聞けると思って待ってはってん。でも二人とも、何も言い出さへんから」
ええ話って? 何の話だ。
「二人、つき合ってどんくらいや。1年たつやろ」
僕はこのとき初めて己が置かれている深刻な事態を飲みこみ、身構えた。
ごぼごぽとコーヒーが落ちる音がキッチンから聞こえる。
「コーヒー飲んだらきちんと話を、ね」
オカンがスリッパを鳴らしながらいそいそとキッチンに向かう。
「マサルくーん、お砂糖とミルクいるう〜?」
ワンオクターブ高音の声でキッチンから呼びかけて来る。
そのブラックコーヒーは、悪魔の飲み物に違いない。
僕の魂と人生を奪う一杯。迫りくる恐ろしい包囲網。家族ぐるみでプロポーズ(させちゃえ)大作戦だ。
前夜、緑茶で平和をもたらしたなどと有頂天になった自分を呪った。
オトンがコーヒーカップの向こう側で無言の圧力をかけてくる。
さあ、言え、言わんか!
「よよよよしえさんと? けっこんを? させて、ください?」
自分の口から出た言葉を疑った。
嘘だよね? ジョークだよね? 誰か取り消して。
ごぽぽぽぽ。コーヒーメーカーから2杯目のコーヒーが落ちた。
「わがままな娘ですがどーぞよろしく!」
コーヒーの湯気の向こうで、悪魔の一家が勝利宣言をした。
お茶はコーヒーに負けた。
コーヒー講座の後半、先生がジャコウネコの話をしながら、2種類のカフェオレを出してくれた。先ほどと同じ、一つはペーパードリップ、もう一つはプレス式で淹れたもの。プレス式のほうがコーヒー粉に湯がつかっている時間が長いぶんだけ、ミルクに負けない濃い豆の味がしてとっても旨い。
それにクロワッサンを合わせると、まるでフランスの朝ご飯。

「コーヒーにはダークな歴史があるんですよ」と先生が言う。
「コピ・ルアク、って聞いたことありますか? 幻のコーヒーと言われている高級な豆の名です。インドネシアでは野生のジャコウネコがコーヒーの実を食べるんです。その種がフンにまじって出てくる。
その昔、インドネシアでコーヒーを作っていた農民たちは、どんなにコーヒーを育ててもヨーロッパに持っていかれちゃうから、自分たちは飲むことができない。しかしある日、猫のフンの中からコーヒーの豆を拾い飲んでみたところ、これが最高に美味しかった。それをヨーロッパの人たちが知り、幻の豆と言われるようになるんです」
結局、現地の農民にとってはますますコーヒーは手が届かないものになってしまったそうな。今では、ジャコウネコを柵の中で飼い、無理矢理コーヒーの実を食べさせて生産する、まがいものコピ・ルアクも出回っているらしい。
美味しいコーヒーは、さまざまな無慈悲な出来事の上に成り立っているのかもしれない。僕の笑顔がそうであるように……。
家に帰ると、さっそくコーヒーを教わった通りの作法で淹れながら、嫁が悪い顔で言った。
「オカンにジャコウネコのコーヒーの話をしたら、『それやったら、犬なんかやめて、ジャコウネコ飼ったらいいやん。豆は売れるし可愛いし、一石二鳥やん』だってさ」
いかにも悪魔が言いそうなことだ。
何度言っても聞き流す母娘だがもう一度言う。
僕は猫アレルギーなんだ。
<前編へ戻る>
◆さくらいよしえ(ライター)
1973年大阪府生まれ。日本大学芸術学部卒。
月刊『散歩の達人』や「さくらいよしえのきょうもせんべろ」(スポーツニッポン)、「ニッポン、1000円紀行」(宅ふぁいる便)など連載多数。著書に『にんげんラブラブ交叉点』『愛される酔っ払いになるための99 の方法 読みキャベ』(交通新聞社)、『東京千円で酔える店』『東京せんべろ食堂』『東京千円で酔えるBAR』(メディアファクトリー)の他、絵本「ゆでたまごでんしゃ」(交通新聞社)、児童小説「りばーさいど ペヤングばばあ」(小学館)など児童向け書籍も執筆。